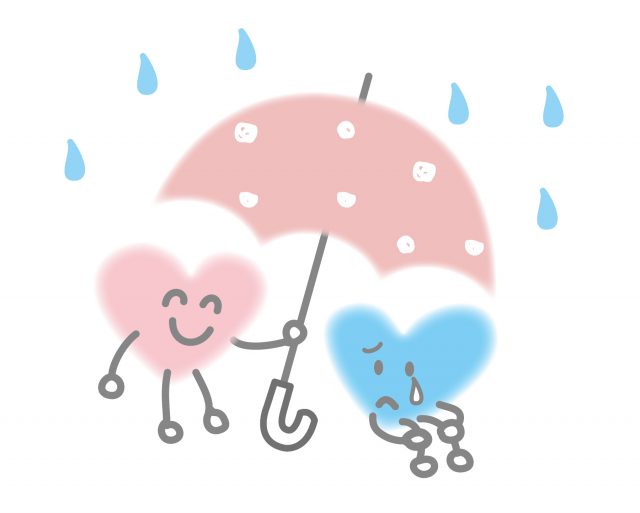以前の私は、学校に通えたら不登校は解決、と思っていました。
ところが、どうして、どうして、そんな単純なものでもないですね。
行き渋りが出始めた時は、一時的なものですぐまた行くだろう、と楽観的に考えていて、それが、その後どんどん深刻になり、登校どころではなくなって・・・。
私の心の変化も、行って欲しい、行ってくれたら嬉しい、から、行かなくてもいい、自分の個性を活かして欲しい、そう変わっていきました。
これがいいのかどうかはわからないですよ。
でも、私がこのように思えたことで、息子も私も心が楽になり親子仲も良くなりました。
ただ、それは私の息子の間でのことで、主人は別。
だから、家族仲、夫婦仲が良かったとは言えなかったです。
日中2人で家にいる間はいいのですが、朝や主人の帰宅後は無言・・・、変な緊張がありましたね。
その主人が今年になって、少しずつ変化してきています。
息子に積極的に話しかけたり、私に対してもとても柔和になりました。
それは今日も続いています。
おそらく、主人も私と同じ心境に近づいたのでしょう。
そう思います。
主人は嫌なことにも負けない強いハートの持ち主。息子の弱さを理解できず、学校に行かないのは、甘えだと思っていたと思います。
でも、学校に行けないのは甘えでも何でもないんですよね。本人とっては苦痛なだけの場所が学校なのです。
行けない、という心を理解し始めたように感じます。
これまで、長かったです・・・
やっとここまで来れたな・・・
そんな心境。
今後に心配や不安がないわけではありませんが、私達親子は不登校というものが、どんなものであるかはわかりました。
そして、少なくとも、苦しみからは脱することができました。
根拠も何もないのですが、学校に行けないからと言って、私は息子が人よりも劣っているとは思えないし、個性も豊かで面白い存在と思っているんですよ^^
ただ、教育は受けていないので、学校の勉強はできませんよ。
ただ、これは習っていないだけのこと。やれば普通に理解できることもわかっています。私達が環境をつくってやれなかっただけなのです。
親子関係は身近で体験できる最高の人間関係の修行、ホント、そう思います。
険悪にもなれますし、心通えば一つにもなれます。
まだまだ日本は学歴偏重主義なところが抜けないので、親も学校に行っていないとどうしても不安なんですよね。
この気持ちもよくわかるんですよ。
この辺りの社会の風潮にもどかしさも感じるし、子供の家にいる時間を陰の時間ではなく、陽の時間にもしたいし、でも、まだまだそのような社会にはなっていないことに、心の中ではギャップを感じている私。
でも、待っていても、いつ変わるかなんてわからないし、誰かがやってくれる約束もありません。
ならば、自分で覚悟も持ってやっていくだけ。
周りがどうであろうと、何を言われようと、動じない心。自分と子供を信じる心。
今の私は、このことを問われている気がしています。
不登校の次なる段階への挑戦ですね。